1.1 物語の時間
まずは短い物語をいくつか紹介しましょう。 それぞれの物語は解釈可能な機械学習のためにいささか誇張されたものです。 もし急いでいるなら、これらの物語は読み飛ばしても大丈夫です。 もし楽しみたいとか、やる気を出したい(ときに失くしたい)ならば、ぜひ読んでみてください!
話の構成は Jack Clark の Import AI Newsletter に掲載されている技術小話から影響を受けています。 もしこれらの物語が気に入って、AI に興味を持ったならば、そのニュースレターに登録しておくことをオススメします。
稲妻は二度と打たない
2030年:スイスの医療ラボ
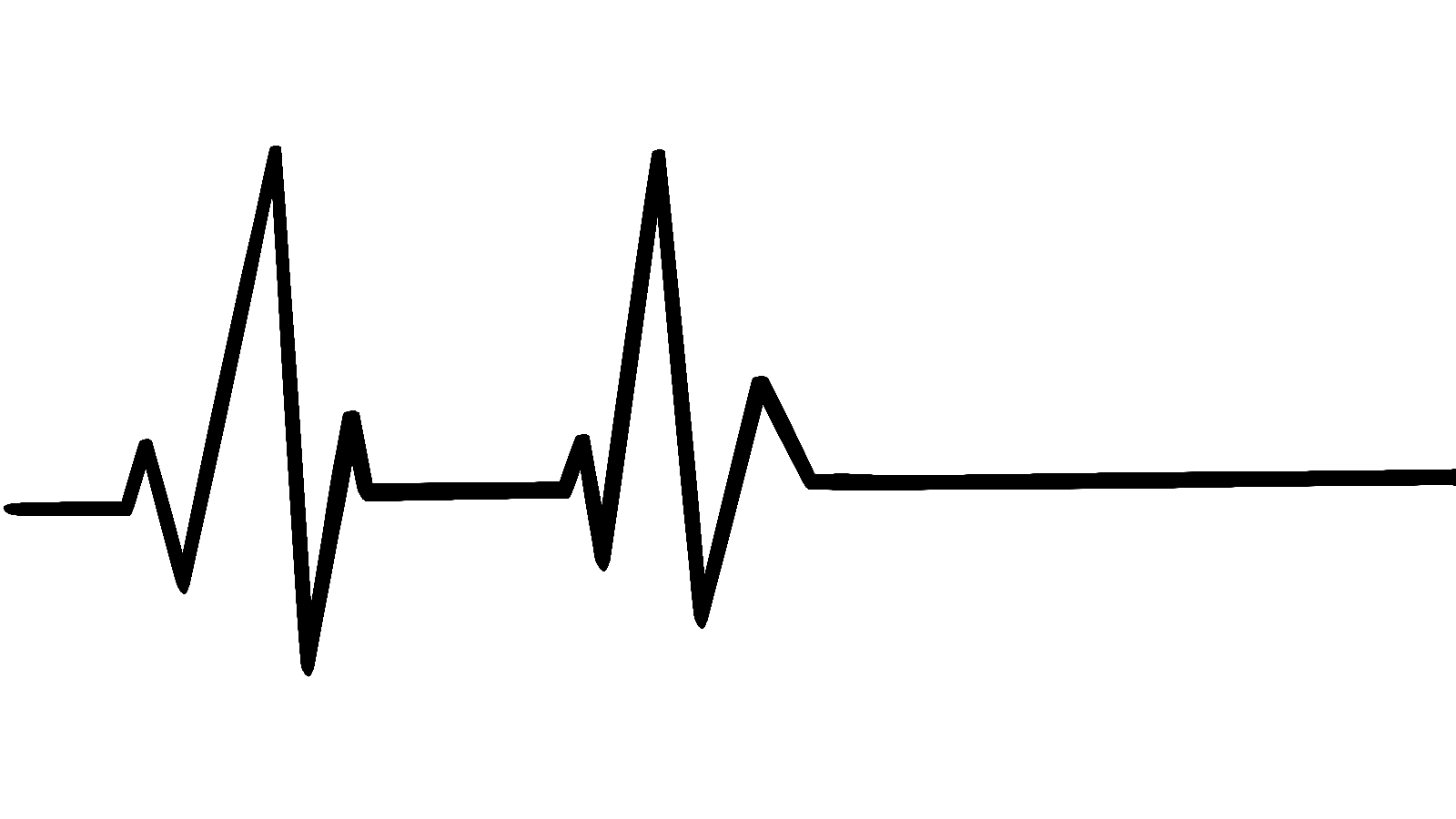
「絶対に、医療ミスなんかじゃありませんでしたよ!」トムは起こった悲劇の中から少しでもマシなことがないか探すかのように言った。 彼は患者の静脈からポンプを引き抜いた。 「彼は医療ミスのせいで亡くなったんじゃないわ」レナが言った。 「この狂ったモルヒネポンプのせいですよ! 余計な仕事を増やしやがって!」トムはポンプの裏板のネジを外しながら不平を言った。 ネジをすべて外し終えると、彼はその板を持ち上げて脇に置いた。 彼はケーブルを診断装置に繋いだ。 「仕事自体に文句を言ったわけじゃないわよね?」レナは彼にからかうような笑みを向けた。 「違いますよ。えぇ違いますとも!」彼は皮肉っぽい低い声で言い返した。
彼はポンプのコンピュータを起動した。 レナはケーブルのもう一方の端を彼女のタブレットに接続した。 「いいわ。診断装置は動作してる」彼女は言った。 「なにがいけなかったのかすごく興味がある」 「John Doe 氏は完全に御陀仏ですね。 この高濃度のモルヒネです。 なんてこった。なんというか……こんなこと初めてです。そうですよね? 普通、壊れたポンプというのはほんのちょっとしか供給しないか、何もしないものです。 決して、いや起こったけど、こんな狂った量の投与はしません」トムは説明した。 「ええ、言わなくてもわかってるわ……ねぇ、これを見て」レナは彼女のタブレットを持ち上げた。 「ここにピークがあるのが見える?これが鎮痛剤を打った効能よ。 見て!このラインは基準値を示してる。 このかわいそうな男性は、彼を17回以上殺せる量の鎮痛剤を血管系に注入されたの。 この私たちのポンプによって。 それに……」彼女は画面をスワイプした。「ここに患者が亡くなった瞬間が記録されてる」 「それで、何が起こったかわかりそうですか、ボス?」トムは彼の上司に尋ねた。 「うーん……センサーは正常なようね。 脈拍、血中酸素濃度、血糖値……データは正常に記録されている。 血中酸素濃度のデータにいくらか欠損値が見受けられるけど、めずらしいことじゃない。 ここを見て。 センサーはモルヒネ誘導体やその他の鎮痛剤によって引き起こされる脈拍の低下とコルチゾール濃度の極端な低下を検知してる」 彼女は診断レポートを次々とスワイプした。 トムは食い入るように画面をじっと見つめた。 それは彼にとって初めての機材故障の調査だった。
「オーケー。これがパズルの最初のピースね。 システムは病院の通信チャンネルに警告を送信するのに失敗している。 警告は発動したのに、プロトコルレベルで拒否された。 それは私たちの落ち度かもしれないけど、病院側の落ち度でもありうるわ。 そのログをITチームに送って」レナはトムに言った。 トムは画面をじっと見つめたまま頷いた。 レナは続けた。 「奇妙ね。 その警告を受けてポンプのシャットダウンも実行されるはずだった。 でも明らかにシャットダウンに失敗している。 きっとバグに違いないわ。 品質管理チームが見逃した。 それもめちゃくちゃ酷いやつ。 多分、プロトコルの問題に関係あるわね」 「それで、ポンプの緊急停止システムがどうにかして故障したのはいいとして、なぜポンプは John Doe 氏にこんなにたくさんの鎮痛剤を注入したのですか?」トムは疑問に思った。 「いい質問ね。 あなたの言う通りよ。 プロトコルの不慮の失敗はさておき、そんなに大量の薬物を投与すべきではまったくなかった。 コルチゾール濃度の低下や他の警告を受けて、アルゴリズムはもっと早くに自分自身で停止するはずだった」レナは説明した。 「雷に打たれるような、万に1つの不運だったかもしれない、ということですか?」トムは彼女に尋ねた。 「いいえ、トム。 もし私が送ったドキュメントに目を通していたなら、このポンプが、センサーからの入力に基づいて完璧な量の鎮痛剤を注入できるよう、最初は動物実験、次に人間で訓練されたことを知っていたかもしれないわね。 ポンプのアルゴリズムは不透明で複雑かもしれないけど、ランダムではない。 それはつまり、同じ状況に遭遇したらポンプは再びまったく同じように動作するということ。 私たちの患者がまた死ぬかもしれない。 センサーからの入力の組み合わせか、望ましくない相互作用かが、ポンプの誤作動を引き起こしたに違いないわ。 だからこそ、私たちはもっと深く掘り下げて、ここで何が起こったのかを明らかにする必要があるの」レナは説明した。
「そうですねぇ……」トムは深く考え込みながら応えた。 「どの道、この患者はそう長くなかったんですよね?ガンかなにかで」 レナは分析レポートを読みながら頷いた。 トムは立ち上がって窓に寄った。 彼は外の、遠くの一点を見つめた。 「おそらく、その機械は彼の痛みから解放されたいという願いを聞いてやったんでしょう。 もう苦しまないように。 雷に打たれるようなものだったかもしれませんが、むしろ幸運だったのかも。 宝くじみたいなもので、ランダムじゃない。 なにか意味があったんです。 もし僕がポンプだったら、同じことをしたでしょう」 彼女はようやく顔を上げ、彼を見た。 彼はまだ外のなにかを見ている。 少しの間、二人は何も言わなかった。 レナは再び画面に目を落とし、解析を続けた。 「いいえ、トム。これはバグよ……ただのクソッタレなバグ」
信用失墜
2050年:シンガポールの地下鉄駅で

彼女は地下鉄 Bishan 駅に駆け込んだ。 頭の中ではとっくに仕事を始めていた。 新しいニューラルアーキテクチャのテストはもうできたはずだ。 彼女は政府の納税義務者の脱税を予測するシステムの再設計に着手した。 彼女のチームはみごとな実装を考案していた。 うまくいけば、システムは税務署だけではなく、テロリスト対策用警鐘システムや、営利法人の登記などさまざまな場面に導入されるだろう。 ゆくゆくはそういった予測を市民の信用度計算システムに統合できるかもしれない。 市民の信用度計算システムは文字通り、それぞれの人が信用できるか判定するものだ。 ローンの採否からパスポート発行までにかかる時間まで、人々の生活のあらゆる面に影響を及ぼすだろう。 エスカレーターをおりる途中で、彼女はチームで開発しているシステムを信用度を計算にいかに統合するか考えていた。
彼女はいつも通り、歩みを緩めることなく、RFID 読み取り機に手をかざした。 良い気分だったが、期待と現実の不一致が彼女の中で警鐘を鳴らした。
遅かった。
彼女は地下鉄の改札に向かったが、鼻をぶつけて尻餅をついてこけた。 開くはずのドアは開かなかった。 驚きながら立ち上がり、改札脇のスクリーンに目をやった。 スクリーンには笑顔のキャラクターと「もう一度お試し下さい」の一言。 彼女のことなど気にせず、他の人は読み取り機に手をかざしてすり抜けていく。 ドアは開いて行ってしまった。 また閉じた。 彼女は鼻をこすった。痛むが出血はない。 彼女はもう一度ドアを開けようとしたが、またしても拒否されてしまった。 おかしい。 公共交通機関を利用するための預金が不足しているのかもしれない。 彼女はスマートウォッチで残高を確認してみる。
「ログインに失敗しました。市民相談所にお問い合わせください」と彼女の腕時計に表示されていた。
お腹を殴られでもしたかのような吐き気が彼女を襲った。 何が起きているのか考えた。 試しに「スナイパーギルド」という携帯ゲームを始めた。 すると予想通りにアプリは自動終了してしまった。 眩暈がして彼女は床にへたりこんだ。
この状況を説明できる方法は1つしかない。 市民の信用度が落ちたのだ。 がっくりと。 ちょっと落ちたくらいなら、飛行機でファーストクラスに乗れないとか、公的文書の取り寄せに通常より時間がかかるとか、少々の不便で済むのだ。 信用度が低いということは、彼女が社会的に危険な存在として認識されたということだ。 そういった人への対策の1つは、地下鉄のような公共施設からの締め出しだ。 政府は信用度が低い人の金銭取引も制限する。 更にはソーシャルメディアでの活動を監視し始め、暴力的なゲームなど一部のコンテンツの利用制限すら課す。 一度落ちた信用度は急激に回復が難しくなってしまう。 どん底まで落ちると這い上がれない。
彼女には信用度が落ちた理由がわからなかった。 信用度は機械学習に基づいて計算されている。 このシステムは、よくオイルを行きわたらせたエンジンのように社会を動かしている。 信用度計算システムの性能は常にモニタリングされていた。 今世紀初頭に比べて機械学習は非常に発展している。 市民の信用度に基づく判断はとても効率的で議論の余地はなかった。 完全無欠なシステムなのだ。
彼女は悲嘆にくれて笑うしかなかった。 完全無欠なシステム。 そうならよかった。 ほとんど失敗しない。 でも失敗した。 彼女は自分がそんな特別な一例だと思った。 システムのエラーだ。 おかげで、社会から見捨てられてしまった。 誰もシステムを疑おうなどとしない。 システムは政府と密に連携していて、社会にまで溶け込んでいて、疑う余地なんてない。 民主主義国家の中には、反民主主義的な活動を禁じている国が少数ながらある。 それは別に危険性が高いからではなく、今あるシステムを不安定にしてしまう可能性があるからだ。 同じ理屈が、今では一般的になった人工知能による統治にも適用される。 現状を危機にしてしまうようなアルゴリズムへの敵対は禁止されているのだ。
アルゴリズムによる信頼度の算出は、社会的に要請されて生まれた。 公益のため、稀な信頼度の誤判定はそれとなく許容された。 スコアの算出には何百もの予測システムやデータベースが利用されていて、彼女のスコアがなぜ落ちたのか説明できなくなっていた。 彼女は自分の足元に大きくて真っ暗な穴が開いたように感じた。 彼女は恐れ、虚空を見つめていた。
彼女の脱税者予測システムが市民の信用度計算システムに取り込まれた、しかし、彼女はそれについて知ることはなかった。
フェルミのペーパー・クリップ
AMS(火星定住歴)612年の火星の博物館で

「歴史って面白くないな」、Xola は友達にこぼした。 青い髪をした少女の Xola は、屋内で彼女の左側を飛ぶプロジェクタ搭載のドローンにだらだらとついていった。 先生は彼女を見て「歴史は重要ですよ」と取り乱し気味に言った。 彼女はまさか先生に聞かれていると思っていなかった。
「Xola、今、何を学びましたか?」と先生は尋ねた。 彼女は慎重に「昔の人は惑星 Earther の資源を使い尽して死んだんでしたっけ?」と聞き返した。Lin という名の女の子が続いた。 「違うよ。彼らは気候温暖化を招いたの。正確には人ではなくコンピューターと機械がね。で、その惑星の名前は Earth(地球)よ。Earther じゃないよ」 Xola はなるほどと頷いた。 先生は少し誇らしげな様子で微笑みながら頷いた。 「どちらも正しいです。ではなぜそんなことが起きたのでしょうか?」 Xola は「人が短絡的で強欲だったからかな?」と首をかしげた。 「機械を止められなかったからよ!」と Lin は思わず言ってしまった。
先生は「今度の答えも両方あってます」と断じた。 「ですが、事態はもう少し複雑だったのです。 当時のほとんどの人は何が起きているか理解していませんでした。 急激な変化に気付いた人もいましたが、取り返しがつきませんでした。 この時代を理解する最も有名な鍵として、書き手不明の詩があります。 この事態に起きていたことを最も明瞭に記しているので、よく聞いていてくださいね。」
先生は詩を読み始めました。 たくさんのドローンが子供たちの前に移動して、それぞれの目に映像を投影し始めた。 映像の中には、切り株だけが残された森の中に立つスーツを着た人がいた。 彼はこう語り始めました。
機械は計算し、予測した
人々は予測の結果に基づいて前進した
人々は機械が学んだ最適解を辿った
最適解は1次元で、局所的で、制約がないものだった
シリコンと人類は指数関数を追い求めた
発展こそ我らが本懐
すべての報酬が得られたとき、
副作用は無視される
すべてのコインが採掘されたとき
自然は置き去りにされる
そして災厄が訪れる
指数的な成長は水泡に帰す泡沫となって弾ける
コモンズの悲劇が繰り広げられる
爆発する
目前で
冷淡な計算と容赦ない強欲が
地球を熱で満たす
何もかもを襲う死に
我々はなす術はない
目隠しされた馬のように、我々は自ら生んだレースの中で競争する
限界に向かって
だから我々は執拗に行進する
機械の一部のように
崩壊も受け入れて
「暗い過去ですね」と呟き、先生は静寂を破った。 「みなさんのライブラリにあげておきますね。 宿題として来週までに暗記しておいてください。」 Xola は溜息をついた。 彼女は小型ドローンを1機つかまえた。 ドローンは CPU とエンジンのおかげで熱を持っていた。 Xola は自身の手に伝わる熱を心地良く感じていた。